2021/09/15
第26回 : アパレル製品のマーケティング その1
アパレル散歩道
2025/11/01


2025.11.1
PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.82】
| 事例 | 服種 | 現象 | 考えられる原因 | 原因分類 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | シャツ(綿100%) | 漂白剤変色 |
| 消費者 |
| 35 | ブルゾン(毛100%) | 金属ファスナー付近の変色 |
| 生産工程 |
| 36 | スラックス(毛100%) | あたり |
| クリーニング条件 |
| 37 | パンツ(綾織) (綿95% ポリウレタン5%) | バギング (ひざ抜け) |
| 商品企画/素材特性 消費者 |
| 事例38 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| メンズ | スーツ | ストライプ柄部分に細かい波打ちが発生した |

図1. ストライプ柄
スーツのイメージ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察 |
|
| 消費者への聞き取り |
|
| 商品に関する調査 |
|
| 原因の推定 |
|
| 確認試験など |
|
| 他に発生しやすい製品 |
|
| 対策 |
|

| 事例39 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| インナー | シャツ | 繰り返し洗濯で紺色が変色した |
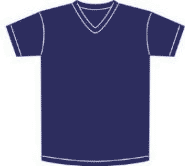
| 項目 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品観察 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品に関する調査 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者への聞き取り |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原因の推定 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認試験など |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類似の事例 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対策 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事例40 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| レディース | スカート | クリーニングによるプリーツ消失 |

図3. プリーツ製品
のイメージ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察 |
|
| 消費者への聞き取り |
|
| クリーニング業者への聞き取り |
|
| 原因の推定 |
|
| 確認試験など |
|
| 類似の事例 |
|
| 対策 |
|
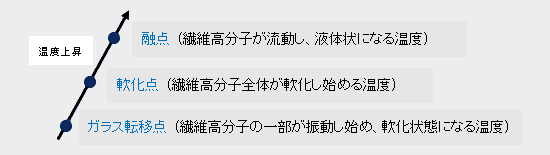
図4. 物質の熱による変化(融点、軟化点、ガラス転移点について)
| ガラス転移点(℃) | 軟化点(℃) | 融点(℃) | |
|---|---|---|---|
| ポリエステル | 70-90 | 238-240 | 255-260 |
| ナイロン | 50 | 180 | 215-220 |
| アクリル | 79 | 190-240 | 明確でない |
| 事例41 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| カジュアル | ニットシャツ | ニットシャツで首の後ろにチクチクを感じた |

図5. 織ネームの例
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察など |
|
| 副資材メーカーなどへの聞き取り |
|
| 原因の推定 |
|
| 発生しやすいネーム |
|
| 対策 |
|

アパレル散歩道
各種お問い合わせCONTACT
サービス全般についてのお問い合わせ
![]()
各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
エコテックス®に対するお問い合わせ
![]()
エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
技術資料ダウンロード
![]()
各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。
よくあるご質問
![]()
試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。
お電話からのお問い合わせはこちら