2022/10/01
第45回 : ケーススタディ①生地の損傷
アパレル散歩道
2025/09/01


2025.9.1
PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.80】
| 事例 | 服種 | 現象 | 考えられる原因 | 原因分類 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | セーター (A100%)※ ※A:アクリル繊維の略号 | 自重伸び (外観変化) |
| 素材特性 表示ミス |
| 27 | ボーダー柄シャツ (C100%) | 強度低下 (破損) |
| 生産管理 生産管理 |
| 28 | ブルゾン (合成皮革) | ドライクリーニング
による硬化 (風合い変化) |
| 素材特性 表示ミス |
| 29 | 青色ジャケット (N100%) | ガス退色 (変退色) |
| 素材/染料特性 生産管理 |
| 事例30 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 紳士服 | スラックス | 1シーズン着用で尻部や膝部がつるつるになった |

図1. 紳士スラックスのイメージ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察 |
|
| 消費者への聞き取り |
|
| 商品に関する調査 |
|
| 原因の推定 |
|
| 対策 |
|
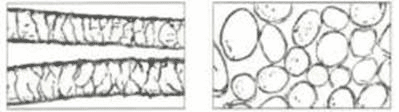
図2. ウール繊維の外観(側面と断面)
側面にはスケール(鱗片)がある
| 事例31 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 紳士服 | ブルゾン | 家庭洗濯で裏地が縮み、裾が内側にカーリングした |

図3. ブルゾンのイメージ
(裏地付)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察 |
|
| 商品に関する調査 |
|
| 消費者への聞き取り |
|
| 原因の推定 |
|
| 確認試験など |
|
| 対策 |
|
| 事例32 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| カジュアル | パンツ | 着用間もない尻部パンク |
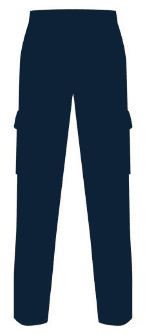
図4. パンツの製品イメージ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察 |
|
| 縫製工場への聞き取り |
|
| 原因の推定 |
|
| 確認試験など |
|
| 対策 |
 図5. 伸び止めテープ使用例 |
| ステッチ形式 | ステッチの特徴 | |
|---|---|---|
| 本縫い | 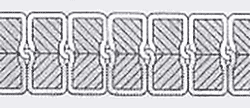 |
|
| 環縫い | 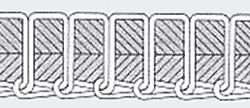 |
|
| 事例33 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| カジュアル | ウールシャツ | リュックの影響による 毛羽立ちと縮み |

図6. チェックシャツとリュックの着用のイメージ
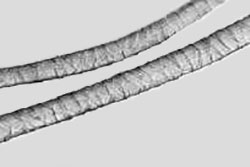
図7. 毛繊維の側面(スケール)
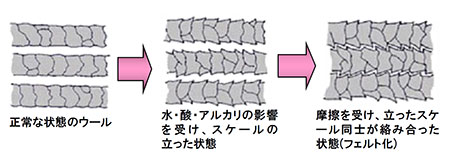
図8. フェルト収縮のメカニズム
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察など |
|
| 消費者への聞き取り |
|
| 素材メーカーへの聞き取り |
|
| 原因の推定 |
|
| 確認試験など |
|
| 対策 |
|

アパレル散歩道
各種お問い合わせCONTACT
サービス全般についてのお問い合わせ
![]()
各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
エコテックス®に対するお問い合わせ
![]()
エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
技術資料ダウンロード
![]()
各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。
よくあるご質問
![]()
試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。
お電話からのお問い合わせはこちら