2022/04/01
第39回 : ものつくり原点回帰シリーズ ~染色 その1~
アパレル散歩道
2025/07/01


2025.7.1
PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.78】
| 事例 | 服種 | 現象 | 考えられる原因 | 原因分類 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | シャツ(E100%) | 在庫中の色移り (汚染) |
| 生産管理 技術限界 商品企画 |
| 19 | 綿パンツ (C100%) | 蛍光増白剤による 白化(変色) |
| 消費者 商品企画 |
| 20 | スウェットシャツ (C100%) | 家庭洗濯による 縮み(外観) |
| 生産管理 消費者 |
| 21 | シャツ (*L70% C30%) * L:麻(Linen)の略号 | フィブリル化による白化(変色) |
| 素材特性 消費者 商品企画 |
| 事例22 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 婦人服 | ブラウス | 背部で破れが生じた |
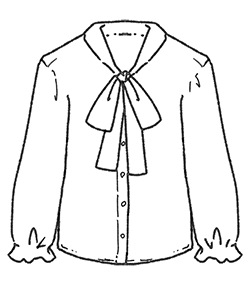
図1. ブラウスの例
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察 |
|
| 消費者への聞き取り |
|
| 商品に関する調査 |
|
| 原因の推定 |
|
| 確認試験など |
|
| 対策 |
|
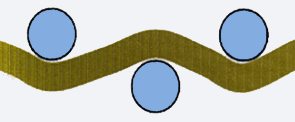
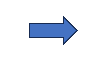
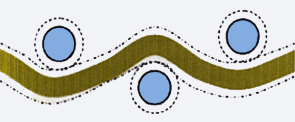
図2. 減量加工前後の糸の変化(イメージ)
| 事例23 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| カジュアル | ニットシャツ | 袖・前身頃を中心に毛玉が発生した |

図3. ピリング現象の例
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察 |
|
| 商品に関する調査 |
|
| 消費者への聞き取り |
|
| 原因の推定 |
|
| 確認試験など |
|
| 対策 |
|
| 事例24 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| カジュアル | ジャンパー | ジャンパーの色がシャツに移った |

図4. デニム製品の
イメージ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察 |
|
| メーカーへの聞き取り |
|
| 原因の推定 |
|
| 確認試験など |
|
| 対策 |
|
| 事例25 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| カジュアル | セーター | 洗濯せずにしまったら黄ばんだ |
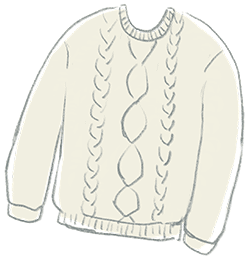
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察など |
|
| 消費者への聞き取り |
|
| 糸メーカーへの聞き取り |
|
| 原因の推定 |
|
| 確認試験など |
|
| 対策 |
|
大阪・関西万博 2025
訪問記 その2 ! はこちらから

アパレル散歩道
各種お問い合わせCONTACT
サービス全般についてのお問い合わせ
![]()
各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
エコテックス®に対するお問い合わせ
![]()
エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
技術資料ダウンロード
![]()
各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。
よくあるご質問
![]()
試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。
お電話からのお問い合わせはこちら