2023/08/01
第55回 : ケーススタディ⑪色の変化~黄変~
アパレル散歩道
2025/01/01
2025.1.1
PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.72】
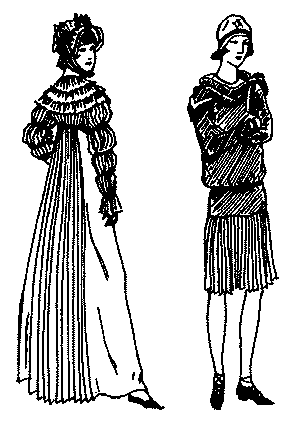
| 綿織物 | 毛(ウール)織物 | 絹織物 | 麻織物 |
|---|---|---|---|
| オックスフォード | ツイード | クレープ | ラミークロス |
| ガーゼ | ウーステッド | サテン | リネンクロス |
| 金巾 シーティング | グレンチェック | シフォン | |
| ギンガム | サージ | シャンタン | |
| ギャバジン | サキソニー | ジョーゼット | |
| コーデュロイ | トロピカル | タフタ | |
| サッカー | ビエラ | 縮緬(ちりめん) | |
| シャンブレー | ポーラ | 紗 | |
| ダンガリー | ピンヘッド | 羽二重 | |
| デニム | フラノ | 絽 | |
| ボイル | フランネル | ||
| ポプリン | へリンボン | ||
| ブロード | メルトン | ||
| ローン | カルゼ | ||
| オーガンジー | アムンゼン |

| 生地名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| オックスフォード | 比較的厚地で柔軟な光沢のある経糸・緯糸ともに2本ずつ引きそろえて織られた平織物が一般的である。名称は英国のオックスフォード(地名)にちなんでいる | ワイシャツや婦人服地に用いられる  |
| ガーゼ | 甘撚り糸の平織で、経緯糸の密度を粗くして織り、さらし後、無糊仕上げしている | 衛生衣料や肌着、ハンカチなどに用いられる |
| 金巾シーティング | 経糸、緯糸に25~50番手の綿糸などを使用した平織物 | 肌着、シーツ、裏地など汎用に用いられる |
| ギンガム | 経糸、緯糸に異なる色糸やさらし糸を使用し、主に格子柄などの平織物。綿ギンガムでは、30~40番手の糸が使用される | ギンガムチェックともいう  |
| ギャバジン | 斜文線が45°以上の経糸密度を多くした2/2 や3/1の綾織物。無地染めが多い 綿ギャバジンのひとつにバーバリーもある | ギャバともいう。スーツ、コート、スラックス、制服などに用いられる |
| コーデュロイ | パイルでたて畝(うね)を表現したパイル織物 | コール天とも言う。ジャケット、パンツ、インテリアなどに用いられる |
| サッカー | 収縮率の異なる経糸を組み合わせて、仕上げに縮ませてしぼ感を表現した平織生地。シャ―サッカーとも言う | 婦人服、子ども服、カーテン地などに用いられる  |
| シャンブレー | 経糸に色糸、緯糸にさらし糸や未さらし糸を使用し、霜降り効果を表現した平織物 | 婦人服、子ども服、カーテン地などに用いられる 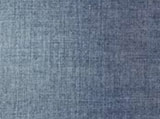 |
| ダンガリー | デニムに似ているが、経糸に白糸、緯糸に色糸を使った綾織物で、表側には、白糸が比較的多く表れている。デニムよりも薄地が一般的である | シャツ地、軽量衣料などに用いられる |
| デニム | 経糸に20番以下の色糸、緯糸に経糸より細めのさらし糸、または色糸を用いた綾織厚地織物 | ジーンズ、作業服、子ども服などに用いられる 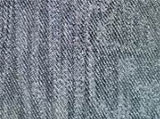 |
| ボイル | 経糸、緯糸に同方向の比較的強い撚り糸を使用したやや粗い薄地平織物 | 風合いは麻のようで、軽くて透けて見える。ブラウス、ワンピース、婦人肌着、スカーフなどに用いられる |
| ポプリン | 経糸の密度を緯糸の1.5倍から2倍に近くして、横方向に畝を出した平織物である | シャツ、スカート、パンツ、ジャケットなど汎用に用いられる  |
| ブロード | 目の詰まった平織物。横方向の畝はポプリンほど目立たない | ワンピース、シャツ、ブラウス、ドレスなどに用いられる 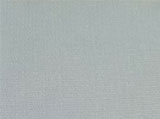 |
| ローン | 経糸、緯糸に細番手の糸を使用した薄地平織物。60~80番の細い糸で構成され、滑らかな触感がある | シャツ、ブラウスなどに用いられる 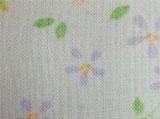 |
| オーガンジー | もともとは綿織物。非常に薄地で織り目が透けて見える織物で風合いは硬い。現在はオーガンジー仕上げとして名を残している |  |
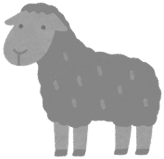
| 綿織物 例 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| ツイード | 太い毛糸を用い、平または綾に織り、縮充起毛をしない粗い感じの紡毛織物のこと。冬の衣料用として用いられる。英国スコットランドが発祥である | ジャケット、ドレスなどに用いられる  |
| ウーステッド | 主に梳毛糸を使用した梳毛織物。サージ、ギャバジン、トロピカル、ポーラ、ドスキン、ベネシャンなどがある | 英国イングランド、ウーステッドが語源である |
| グレンチェック | 濃色と淡色の糸2本ずつと4本ずつを交互に配した格子柄 | グレナカート・チェックの略称  |
| サージ | 細い梳毛糸で45度斜め模様の綾織物。羽毛立たないように、表面の毛を刈り取るクリア仕上げをしている。語源はラテン語のsericaで、絹を意味していた | 学生服に多用され、スーツや礼服にも用いられる |
| サキソニー | 紡毛糸または梳毛糸を平織りや斜文織りにし、縮絨したあと、軽起毛して短く刈りそろえた織物 | 風合いはフランネルとメルトンの中間である |
| トロピカル | 細い梳毛糸を使用した平織物で、夏用の薄地織物。英国から熱帯地域に輸出されていた |  |
| ビエラ | もともと綿50%、毛50%混紡糸の2/2綾織でフランネル仕上げしたもの | フランネル仕上げとは、縮充させ、毛羽を抑えた独特のやわらかさで、なめらかな風合いを出す加工 |
| ポーラ | 経糸、緯糸にポーラ糸(強撚三子糸)を使用した密度の粗い平織物 通気性を有するため、夏用スーツ、ジャケット、パンツなどに用いられる |  |
| ピンチェック | 細かい格子柄もしくは二色の糸を細かく格子柄に織った生地のこと。ピンの頭を並べたような格子織物である。ピンヘッド・チェックともいう | 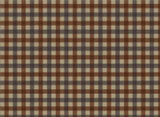 |
| ベネシャン | 朱子または綾の変化組織で用いられる光沢のある織物で、通常の朱子織より厚手である。イタリア/ベネチアが由来とのこと | 織組織は5枚朱子が多く、ドレープ性に優れ、スーツやドレスなどに用いられる |
| フラノ | 平織物や綾織物で軽く縮充・起毛した比較的薄地の紡毛織物。フランネルの一種で、通常フランネルは紡毛糸を用いて作られるが、フラノは梳毛糸を使い、よりソフトに仕上げたフランネルをフラノという | 紳士スーツなどに用いられる  |
| フランネル | 紡毛糸使いの柔らかい毛織物のこと。 紡毛糸は梳毛糸と異なり、太く毛羽立った糸で、ざっくりした起毛感と保温性が特徴である | シャツ、スーツ、パジャマ、寝具などに用いられる |
| へリンボン | 杉綾の織物。織り目がニシン(herring)の骨(born)に似ていることが語源。紳士・婦人スーツ、帽子など汎用に用いられる |  |
| メルトン | 紡毛織物の一種で、縮充加工して、地組織を毛羽で覆った紡毛織物。毛羽は揃っていて表面は平滑で、フェルトのように柔軟である | 紳士・婦人コートなどに用いられる |
| カルゼ | 経糸に霜降りの双糸または杢糸(もくいと)、緯糸に単糸を使用した綾織の毛織物のこと | コートなどに用いられる。カージー(kersey)とも呼ばれ、英国東部のカージー村が由来と言われる |
| アムンゼン (梨地織) | もともとは梳毛織物の一種で、地薄な高級織物 |  |
| フェルト | 羊などの動物の毛を圧縮してシート状にした繊維素材の総称。最近では、廉価版として化学繊維(特にポリエステル)を使った素材もある |  |

| 絹織物 例 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| クレープ | 緯糸に撚糸を使用し、布にしぼを表した平織物の総称。精錬後、強撚糸の特徴である元に戻ろうとする力でしぼが再現される。薄手で軽く、通気性がよく、夏物衣料に用いられる |  |
| サテン | 朱子織物のこと。経糸が表面に多く出た織物を経朱子、緯糸が多く出た織物を緯朱子という | フォーマルドレスや和装の帯など正装アイテムで用いられる |
| シフォン | 経糸、緯糸に撚りの弱い生糸を使用し、比較的粗く織り上げた平織物 | 表面にシボと透け感のある平織物である。ドレス、ブラウス、スカーフなどに用いられる |
| シャンタン | もともとは、緯糸に絹の節糸を使用して不規則な節を出した絹織物 | 語源は、中国山東省(Shantung)から |
| ジョーゼット | 経糸、緯糸にSZ強撚糸を2本ずつ交互に使用し、しぼを現した比較的密度の粗い平織物。クレープや縮緬の一種で、ブラウス、ドレス、羽織、装飾物に用いられる |  |
| タフタ | 薄くて高密度の平織絹織物のこと。経糸は高密度に、緯糸はやや太い糸を使用して、細かいよこ畝を表現している。もともとは絹織物だが現在ではレーヨンやナイロン、ポリエステル、アセテートも使用されている | 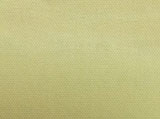 |
| 縮緬 (ちりめん) | 絹の平織物で、経糸に生糸、緯糸に生糸のS・Z強撚糸を交互に打ち込み、表面にしぼを出した織物の総称 | 和服地に用いられる |
| 紗 (しゃ) | 2本の経糸が、緯糸1本ごとに、もじり目を作る織物で、からみ織の1種である。「もじる」は、ひねるの意味 | 着物、夏用の羽織、帯、襦袢(じゅばん)などに用いられる。通気性に優れる。絽に比べると透け感は大きい |
| 羽二重 (はぶたえ) | 日本を代表する絹織物で、経糸、緯糸に無撚の生糸などを使用している。細い経糸を2本にして製織するため、柔軟な光沢のある織物となる | 語源は、織機の筬(おさ)の一羽に経糸を2本通すことからきている。和服裏地などに用いられる |
| 絽 (ろ) | 紗と平を組み合わせたからみ織物で、通気性に優れカーテン地などに用いられる | 夏物の着物として用いられる  |
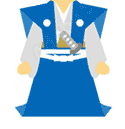
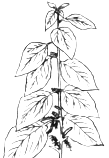

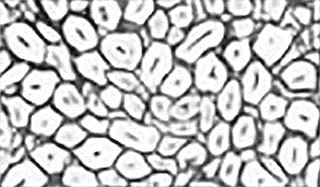
図2 麻繊維の外観(左)、側面(中央)、断面(右)
| 麻織物 例 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| ラミークロス | ちょ麻で織られた生地。古くから、越後上布、小千谷縮、近江上布、能登上布などがある | ちょ麻繊維は、長くて太く、現在は南方系地域でも栽培されている。昔から東洋の麻ともいわれた |
| リネンクロス | 亜麻で織られた生地。古くメソポタミア地域を起源とし、古代エジプトでも使用されていた | 亜麻繊維は、短くて細く、現在では北方系地域でも栽培されている。亜麻科の植物から作られる植物繊維で、世界の主産地はフランス北部やベルギー、アイルランドなどが中心となっている |

アパレル散歩道
各種お問い合わせCONTACT
サービス全般についてのお問い合わせ
![]()
各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
エコテックス®に対するお問い合わせ
![]()
エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
技術資料ダウンロード
![]()
各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。
よくあるご質問
![]()
試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。
お電話からのお問い合わせはこちら