2022/11/01
第46回 : ケーススタディ②縫い目の損傷
アパレル散歩道
2025/08/01


2025.8.1
PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.79】
| 事例 | 服種 | 現象 | 考えられる原因 | 原因分類 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | ブラウス (E100%) | 着用時の破れ (破損) |
| 生産管理 企画設計 消費者 |
| 23 | ニットシャツ (C70% A30%) | ピリング (外観変化) |
| 消費者 商品企画 技術限界 消費者 |
| 24 | デニム (C100%) | 着用時の 色移り |
| 生産管理/技術限界 品質管理/技術限界 技術限界 |
| 25 | セーター (W100%) | 黄ばみ |
| 素材特性 生産/技術限界 生 産 技術限界 |
| 事例26 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 婦人服 | セーター | ハンガー干しで着丈や袖丈が伸びた(自重) |
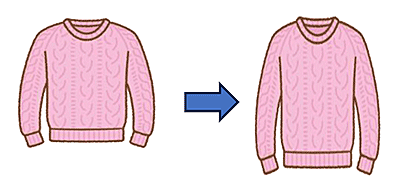
図1. セーターの伸び切り(イメージ)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察 |
|
| 消費者への聞き取り |
|
| 商品に関する調査 |
|
| 原因の推定 |
|
| 対策 |
|
| 例 | 発生の事例 | 原因 |
|---|---|---|
| 1 | ざっくりしたウール100%セーターをハンガーにかけて保管していたら、首回りや丈が伸び切っていた | 自重による伸び |
| 2 | 綿100%スウェットシャツの襟(リブ編み)が繰り返しの着用で伸びきった | ニット組織の伸び切り |
| 3 | 綿95%ポリウレタン5%のニット肌着(天竺)で着用を繰り返していたら、全体に巾・丈とも伸びきった | 弾性の低下 |
| 事例27 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| カジュアル | Tシャツ | 黒色部に破れが生じた |

図2. ボーダーシャツのイメージ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察 |
|
| 商品に関する調査 |
|
| 消費者への聞き取り |
|
| 原因の推定 |
|
| 確認試験など |
|
| 対策 |
|
| 事例28 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| カジュアル | 合成皮革ブルゾン | ドライクリーニングに出したら硬化した |

図3.
合皮ブルゾンのイメージ
| 樹脂の種類 | 耐ドライクリーニング溶剤性 | 耐低温性 |
|---|---|---|
| ポリウレタン樹脂 | 〇 | 〇 |
| ポリ塩化ビニル樹脂 | ×硬化あり | ×硬化あり |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察 |
|
| 素材メーカーへの聞き取り |
|
| クリーニング店への聞き取り |
|
| 原因の推定 |
|
| 確認試験など |
|
| 対策 |
|
| 事例29 | ジャンル | 服種 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 紳士服 | ジャケット | 石油ストーブで乾かしたら 赤っぽく変色した |
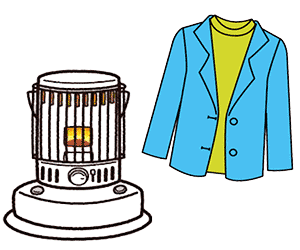
図4. 石油ストーブ側での
乾燥のイメージ

図5. ガス退色の一例
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品観察など | 変退色の原因を確認するため、以下の点を目視で調査する。
|
| 消費者への聞き取り |
|
| 原因の推定 |
|
| 確認試験など |
|
| 対策 | <材料の事前評価>
|

アパレル散歩道
各種お問い合わせCONTACT
サービス全般についてのお問い合わせ
![]()
各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
エコテックス®に対するお問い合わせ
![]()
エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。
技術資料ダウンロード
![]()
各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。
よくあるご質問
![]()
試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。
お電話からのお問い合わせはこちら